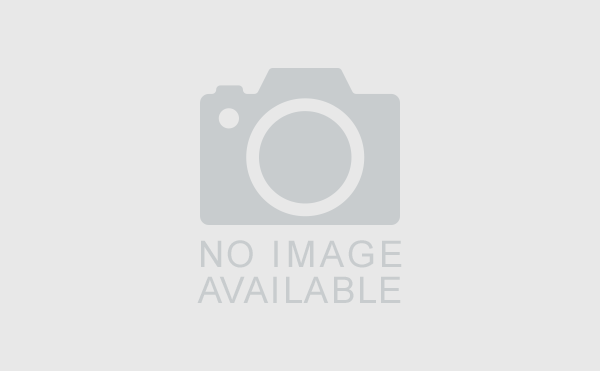第2章 実施体制の整備
第2章 被害認定業務の実施体制の整備
1.★調査計画の策定
被害の情報を集め、その情報をもとに、調査対象、調査地域等調査方針を定め
、調査件数等を想定して、調査計画を立てます。この際、以下のようなフレー
ムを活用することが考えられます。
この項目で検討する事項) *分譲マンション(共用部・専有部)
①調査業務経験のある地方公共団体への相談
②被害情報の収集
③関連情報の収集
④調査方針の設定
⑤調査件数の想定
⑥全体スケジュールの確認・調整
①調査業務経験のある地方公共団体への相談
②被害情報の収集
調査方針を決定するため、災害の規模(被害棟数)や被害集中地域等、必要
な被害状況に関する情報を収集します。
情報の収集にあたっては、市町村の災害対策本部、消防、警察、都道府県等
の関係機関と連携するほか、住宅地図等を持って実際に現場に出向き、被害状
況を確認します。
また、被災建築物応急危険度判定(応急危険度判定)の判定結果(調査表や判
定実施区域図等)を地図に反映させたり、現地調査や航空写真、ドローンによ
る空撮映像等を活用し、被害の集中している地域を把握します。
◇ 水害の場合、災害直後の被害状況調査で目視により浸水深(床上・床下)を
把握しておくと、その内容を調査に利用する等により、調査の効率化が図れる
場合があります。
◇ 空撮画像をAIにより解析して得られた浸水範囲や浸水戸数を活用することに
より、調査計画に向けた被害規模推定の精度向上と効率化・迅速化が図れる場
合があります。
③関連情報の収集
周辺の被災地方公共団体の調査の方針と調査スケジュール、講じられる各種
被災者支援措置と支援措置の区分、被災者からの要望について情報を収集し
ます。
◇ 被災者支援策には、災害発生後に決まるものもあります。被災者への広報事
項が刻々と変わると被災者も混乱しますので、できれば初期の段階で支援策を
整理することが望ましいと考えられます。
*参考:関連情報の収集が不足した事例
・ 災害翌日からとにかく被害認定調査を開始したが、具体的な罹災証明書の交
付時期や罹災証明書により受けられる支援について、職員も理解していない
状況であったため、住民からの問い合わせに答えられない状況だった。
・ 応急危険度判定で「危険」と判定された建物について、住民が「全壊」と勘
違いして、建物の除却申請を行ってしまったケースがあった。職員も応急危険
度判定との違いや、被害認定調査、罹災証明書交付のことについて十分な知識
がなかった。
④調査方針の設定
調査方針として、a)調査対象、b)調査対象地域、c)被害区分、d)調査結果の伝
達方法、e)調査手法を決定します。 調査方針は、周辺の被災地方公共団体と
も情報交換を行うなど、よく調整します。
*参考:複数市町で調査方針を統一することができた例(兵庫県)
・ 佐用町、宍粟市、朝来市、いずれの市においても被害認定調査のノウハウを
持った職員が少なく、兵庫県職員が管理のサポートを行うとともに、各市町に
対し調査方法の説明を行った。その結果として、調査方法を統一することがで
きた。
a)調査対象
調査対象を決めます。
◇ 調査対象について漏れがないようにすることが、調査の円滑化や迅速化のた
めに必要です。
■被害が軽微なものの取扱い
· 被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する物件につ
いては、自己判定方式を採用して調査を簡素化する、あるいは現地調査そのも
のを行わないことも考えられます。
· 自己判定方式を実施することで、「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当す
る住家の被害認定調査の事務手続を軽減することができるため、結果的に罹災
証明書の交付の迅速化につながります。
· ただし、自己判定方式は申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害で
あることに合意できることが前提となるため、合意が得られない場合や、被災
した住家を撮影した写真からだけでは、被害が軽微で明らかに「準半壊に至ら
ない(一部損壊)」と判断ができない場合は、通常の現地調査を実施し、その
結果に基づいて判定を行うこととなります。
· なお、受付窓口で写真を元に「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断できる
かどうかを判断する必要があるため、受付窓口の担当者も被害認定調査に関
する基本的な知識等を身につけておくことが必要となります。
*参考:自己判定方式の活用により調査件数を大幅に減少させた例
(千葉県香取市)
・ 罹災証明書の交付を行った件数のうち、約9割を自己判定方式で対応する
ことができ、現地調査件数を大幅に減少させることができた。
*水災(床上方式)
*参考:地震保険の損害状況申告方式について(一般社団法人日本損害保険
協会)
・ 地震保険の契約者は、被災した建物および生活用動産の損害状況を専用の
損害状況申告書に記入し、損傷個所の写真を添付して損害保険会社に申告する。
(各社失敗)
b)調査対象地域
■当該市町村全域(全棟調査)/一部地域は全棟+申請建物/申請建物のみ
c)被害区分
被害区分を決めます。
■被害認定基準における被害区分/その他
· 被害認定基準における被害区分:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準
半壊、準半壊に至らない(一部損壊)
· ◇ 当該区分は、被災者生活再建支援金、災害救助法に基づく制度等の適用の
判断に活用するため記載することが必要となります。
◇ 迅速で円滑な被災者支援を実施するため、条例を制定し、税の減免区分と
住家の被害認定における判定結果を合致させた例もあります。
d)調査結果の伝達方法
調査結果を、被災者に対して、いつ伝えるかを決めます。
· 原則として調査時は被災者には判定結果は伝えず、罹災証明書交付時点で伝
えます。
◇ 地震第1次調査のように、多くの棟数を短期間に処理する場合、不慣れな
調査員もいるため、一旦、持ち帰って調査水準を統一することも大切であり、
罹災証明書交付時に説明することが良いと考えられます。
*その場で協定しない
e)調査手法
「災害の被害認定基準について」(令和3年6月24日付け府政防第670号内閣
府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、住家の被害認定調査を円滑かつ
迅速に行うため、標準的な調査方法及び判定方法を示した「災害に係る住家
の被害認定基準運用指針」(平成13年7月作成、令和3年3月最終改定)を
踏まえ、適切に住家の被害認定調査を実施します。
■地震による被害の場合
調査手法として、第1次調査から実施するか、第2次調査から実施するかを
決めます。
· 第1次調査から実施:まず第1次調査として外観目視調査を行い、申請があ
った場合に第2次調査として、被災者の立会いのもと、外観目視調査及び内部
立入調査を実施します。
· 第2次調査から実施:第1次調査は実施せず、最初から第2次調査を実施し
ます。
◇ 調査棟数が少なく、余震も少なく、住家内部に立ち入ることが可能である
と判断できる場合には第1次調査を実施せず、最初から第2次調査を実施する
こともできます。
第1次調査票の種類には、A版とB版があります。
· A版:運用指針に最も準拠している第1次調査票。損傷程度別の面積から損害
割合を算出します。
· B版:A版よりも簡略化されている第1次調査票。損害割合イメージ図を用いて
損害割合を算出します。
◇ 調査票A版やB版を用いる場合でも、各地方公共団体で使いやすいよう調査票
番号にQRコードを入れたり、被害区分を増やしている場合には、その判定の欄
を設けたりする等の工夫をすることも良いでしょう。
■水害による被害の場合
調査手法として、第1次調査から実施するか、第2次調査から実施するかを決
めます。
· 第1次調査から実施:木造・プレハブで戸建ての1~2階建の場合には、第1
次調査を実施します。第1次調査では、外観の損傷状況及び浸水深の目視によ
る把握を行います。
第1次調査を実施した住家の被災者から申請があった場合には、第2次調査を
実施します。なお、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外
力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合と、そうでない場
合とで判定の方法が異なることに留意します。
◇ 調査棟数が少ない場合には、第1次調査を実施せず、第2次調査から実施す
ることもできます。
· 第2次調査から実施:木造・プレハブ戸建ての1~2階建て以外の場合には
第1次調査は実施せず、第2次調査から実施します。第2次調査では、外観か
ら一見して全壊と判定できる場合を除き、原則として被災者の立会いのもと、
外観目視調査及び内部立入調査を行います。
◇ 第1次調査の対象とならない家屋(集合住宅等)は、第2次調査から実施
することになりますが、罹災証明書の交付を遅らせないため、第1次調査と並
行して調査を進めることが必要と考えられます。
■風害による被害の場合
地震や水害の場合とは異なり、第1次調査と第2次調査の区分はありません。
調査手法は、外観から一見して全壊と判定できる場合や準半壊に至らない
(一部損壊)と判定できる場合を除き、原則として被災者の立会いのもと、
外観目視調査及び内部立入調査を行います。
※火災による被害の場合については、消防法に基づく火災損害調査の例により
調査を行うことが考えられます。
■被害程度の判定における写真等の活用について
発災前後の航空写真等が入手でき、これらを活用することが調査の効率化・迅
速化に資すると判断される場合には、当該航空写真等を活用して判定すること
が可能です。
例えば、航空写真等から発災後の当該住家の屋根の軸がずれている又は屋根の
位置が変わっているなど、明らかに住家全部又は一部の階が全部倒壊している
等一見して「全壊」と判定できる場合には、当該航空写真等により判定した結
果をもって「全壊」の被害認定を行うことも可能です。
なお、航空写真等からだけでは判定できない場合には、現地調査を行うことと
なります。
また、「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する物件に自己判定方式が活用
可能であることを示しましたが、「準半壊に至らない(一部損壊)」以外でも、
住家の被害の程度の判定を的確に実施することが可能であれば、被災者や民間
企業等から提供を受けた住家の損壊状況が確認できる写真等を用いて、被害程
度を判定することが可能です。
*参考:航空写真等を活用して判定した事例(平成30年西日本豪雨)
・土砂災害計画区域などの調査員の立ち入りが難しいエリアにおいては、航空
写真を活用した判定を行い、流出など明らかに「全壊」と判断できる事例につ
いて適用した。
・判断に迷う場合には現地に赴いて対応した。
⑤調査件数の想定
④で設定した調査対象、調査手法に基づき、被害範囲にあると見込まれる住家
の件数を算出します。
⑥全体スケジュールの確認・調整
各種の被災者支援施策のスケジュールを勘案し、罹災証明書交付開始日を設定
します。
罹災証明書交付開始日と各種被災者支援施策のスケジュールについて、全庁で
共有し、齟齬がないようにします。
全体スケジュールの確認を行う場合、特に調査や罹災証明書の交付の遅れにつ
ながるような抜け漏れがないように留意する必要があります。
被害が複数の市町村にわたる場合には、都道府県とスケジュールを調整します。
参考:概略全体図:重要(例)

2.調査体制の構築
災害規模等に応じて被害認定調査の体制を構築します。被災市町村のみでは
必要な人員を確保できない場合、応援を依頼します。
(この項目で検討する事項)
①被害認定調査の体制の設定
②人員計算
③★庁内での人員確保
④★応援職員の要請
⑤★応援職員の受入
①被害認定調査の体制の設定
被害認定調査の体制を確立します。
主な業務としては、全体の統括、被害認定調査の指揮・コーディネート、現
地調査、調査後の処理があります。災害規模や災害対策本部・被害認定調査担
当課の体制・人数に応じて体制を設定します。
また、相談窓口の設置、相談窓口の担当部署等について、検討します。
地震や水害の第2次調査や風害の調査といった内部立入調査を行う必要が
ある場合、調査実施時に被災者の立ち会いが必要となります。そのため、被
災者の在宅率が高い休日にまとめて調査を実施することが調査期間の短縮に
つながります。
実際の体制整備にあたっては、庁内の他部署の職員や他の地方公共団体等の
応援職員などを活用し、休日により多くの調査を実施できる体制を構築する
ことも有効です。


②人員計算
想定される調査棟数、調査期間から、確保する調査人員を算出します。
この際、1班あたりの班人数を想定しま
想定される調査棟数、調査期間から、確保する調査人員を算出します。
この際、1班あたりの班人数を想定します。
◇ 未経験者が多い場合は、当初、研修等の時間が必要になります。
◇ 市街地と郊外部では、移動時間により調査可能な棟数が変わってきます。
また、地震木造第1次調査の場合は一見全壊の割合、水害木造調査の場合は
床下浸水の割合で異なります。
概算で人員計算を算出し、人員手配をした後、実際の調査を進めながら日々
調整することが必要となります。
◇ 内部立入調査の場合、居住者が立ち会うため、居住者対応により調査時間
が長くなります。
◇ 上記のほか、1日に調査できる棟数は、日没時間のほか、雨天や暑寒等の
天候にも左右されます。
◇ 1班2人の場合:調査を行い調査票への記入担当と、写真の撮影担当等と
いった形で、分担して調査を行います
◇ 1班3人の場合:1人が現場の案内や住民への対応等を担当することで、
他の2人が調査票への記入や写真撮影等に専念することができます。
危険があった場合や、住民への応対、調査の精度や効率を考えると、単独
での調査は望ましくないと考えられます。


<調査スピード例※>
■地 震 木 造 第1次調査 10棟/日・班
地 震 木 造 第2次調査 5棟/日・班
地 震 非木造 第1次調査 5棟/日・班
地 震 非木造 第2次調査 3棟/日・班
■水 害 木 造 第1次調査 15棟/日・班
水 害 木 造 第2次調査 5棟/日・班
水 害 非木造 3棟/日・班
■風 害 木 造 5棟/日・班
非木造 3棟/日・班
※手配人員数を算出するための目安時間です。
※調査対象家屋間の移動距離によって調査スピードは異なります。
<計算式>
■木造 第1次調査
・ 30,000棟 ÷ 10棟 =3,000日・班
20日間で被害認定調査を終了、1班2人体制、10班に1人コーディネーター
を入れるとすると
・ 必要な1日当たりの班数 3,000日・班÷20日間=150班
・ 必要な1日あたりの調査員数 150班×2人=300人
・ コーディネーター 15人
■非木造 第1次調査
・ 10,000棟 ÷ 5棟 =2,000日・班
20日間で被害認定調査を終了、1班2人体制、10班に1人コーディネーターを
入ると
・ 必要な1日当たりの班数 2,000日・班÷20日間=100班
・ 必要な1日あたりの調査員数 100班×2人=200人
・ コーディネーター 10人
③★庁内での人員確保
調査員確保の考え方を検討します。
◇ 同じ人が長期間、調査員として担当できれば、被害認定調査について理解が
深まり、精度の高い調査を円滑に行うことができます。
④★応援職員の要請・受入
庁内のみでは必要な人員を確保できない場合、a)他の地方公共団体、b)民間
団体等へ応援を依頼します。
具体的な内容は、「6.被害認定調査に関する受援」を参照して下さい。
3.★資機材等の調達
被害認定調査を実施するにあたり、調査場所の整備、調査資機材の準備を行い
ます。
(この項目で検討する事項)
①空間の確保(作業部屋)
②調査資機材の調達
③移動手段の確保
①空間の確保(作業部屋)
被害認定調査を推進するための空間として、a)コーディネーターの作業スペー
ス、b)調査員の作業スペース、c)ミーティングスペースを確保します。
②調査資機材の調達
被害認定調査に必要なa)資機材、b)調査票を確保します。また、必要に
応じてc)調査済証、d)調査員証を用意します。

* プリンター
* スキャナー

③移動手段の確保
現地までの移動手段を確保します。
◇ 原則、公用車を利用しますが、不足する場合は、レンタカーや応援団体の
公用車の利用を検討します。また、都道府県から車両の提供を受けた例もあり
ます。
4.★研修の実施
各調査員に具体的な調査手法を正確に理解してもらい、調査員の質をなるべく
一定に保ち、調査結果のばらつきを極力排除することを目的として、調査に参
加する調査員全員を対象に研修を実施します。研修の実施方針として、研修に
おいて学ぶ内容と、研修の実施方法をあらかじめ検討する必要があります。
(この項目で検討する事項)
①研修内容の決定
②研修方法の決定
①研修内容の決定
研修において、実際の調査を行う前に、調査員に理解してもらう内容や項目
を検討します。
◇ 行政職員宅が被災した場合に、座学の研修に加え、当該職員の承諾を得て、
実地研修を行った事例もあります。
応援職員も含めて研修を適切に実施できないと、正しい調査が実施できず手
戻りとなってしまうケースもあります。
*参考:研修内容・項目の例
・ 被害認定調査の位置づけ・重要性
⇒被害認定調査の位置づけや調査結果の利用範囲、重要性等を理解してもらい
ます。
・ 調査方法の説明
⇒被害認定調査の具体的な判定方法、調査票への記入方法等について、理解し
てもらいます。
・ 写真撮影のルール
⇒写真撮影にあたり、その後の整理のしやすさ等の観点から、撮影順序や留意
点を整理し、伝達します。
・ 調査にあたっての心構え
⇒調査を行うにあたっての基本的な心構えや注意事項等を確認します。
・ 罹災証明書、当該地方公共団体で講じられる被災者支援策について
⇒交付開始時期、交付場所、申請方法、申請窓口、罹災証明書によって受ける
ことができる支援制度について情報を伝えます。支援策が確定していない場合
は、今後の広報方法等住民に伝える方法を決めておきます。
・ 住民対応の方針やルールその対応について共有します。
⇒住民から多く寄せられる問い合わせ等に対し、統一した対応ができるよう
にします。
・ その他、地域的な事情等
⇒当該地方公共団体における被害認定調査の方法及び調査票の具体的な記入
方法等を共有します。
②研修方法の決定
a)研修担当者、b)研修対象者、c)開催頻度、開催時間、会場を決定し、
研修を実施します。
a)研修担当者
研修担当者を決めます。
<研修資料等>
・ 災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料(損傷程度の例示:内閣
府)
・ (映像資料)住家の被害認定調査(地震による被害)【木造・プレハブ】
(http://wwwc.cao.go.jp/lib_012/jyuka_higaininteichousa.html)
*参考:ビデオ等による研修(兵庫県宍粟市)
・ 調査初日から3日目までは、調査開始前に県担当者が応援職員等に対して
ガイダンスを実施し、調査方法等を説明した。4日目以降は、そのガイダンス
の様子をビデオに撮影し、初めて来る応援職員に見てもらい、調査方法等を理
解してもらった。
b)研修対象者
研修を行う対象を決定します。
◇ 基本的には過去の被害認定調査の経験の有無にかかわらず、当該被害認定調
査に参加する前に必ず全員、受講することとします。
◇ 調査結果のばらつきが生じないよう、研修を通じて調査員の習熟度合をなる
べく一定に保つ必要があります。
◇ 調査の公平性を期す上でも、各調査員に具体的な調査手法を正確に理解して
もらうことが重要です。
◇ 大規模な災害で研修に十分な時間を確保できない場合は、調査着手時の調査
員のみ受講(過去に受講済みの調査員はDVDや映像資料の視聴等簡易なもので
も可)することとし、その後追加される調査員は実務経験のある調査員に同行
してOJTにより経験を積むことで研修に代えることも考えられます。
<災害に係る住家の被害認定(内閣府ホームページ)>
http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html
c)開催頻度、開催時間、会場
研修の開催頻度や開催時間、会場を決めます。
5.★広報
被災者及び住民に向けて、被害認定調査及び罹災証明書に関する広報を行い
ます。また、マスコミへの対応を行います。
(この項目で検討する事項)
①被害認定調査実施に関する広報
②支援制度や罹災証明書交付スケジュール等に関する広報
③マスコミへの対応
①被害認定調査実施に関する広報
被災者支援を受けるためには、被害認定調査を行う必要があり、建物の除去
や被害箇所がわからないような修理、片づけ等をしてしまうと調査ができない
ため、可能な限り被災者が被害状況について写真撮影を実施し、保存しておく
よう周知を徹底します。(「住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意
事項について」(令和2年7月5日付け
事務連絡内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者生活再建担当)
通知))
◇ 水害、風害においては、被災後の片づけが迅速に行われることが多いこと
から、被災者には、片づける前に、水害の場合は「浸水深」と「被害箇所」、
風害の場合は「被害箇所」がわかる写真を撮影しておくよう広報すると良い
でしょう。
②支援制度や罹災証明書交付スケジュール等に関する広報
<災害に係る住家の被害認定(内閣府ホームページ)>
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf
6.★被害認定調査に関する受援
被害認定調査において、他の自治体等からの支援を受けることは、限られた時
間の中で調査を進める上で非常に重要となります。ここでは、被害認定調査の
受援時において必要となる業務内容について検討します。
(この項目で検討する事項)
①受援の流れの全体像
②応援の要請
③応援職員の受入体制の確保
④応援職員の受入
⑤応援職員の管理
⑥応援の終了と精算
①受援の流れの全体像
受援は、「応援の要請」「応援職員の受入体制の確保」「応援職員の受入」「応
援職員の管理」「応援の終了と精算」の流れで進行します(詳細は次項から順
次説明)。
◇ 「応援の要請」では、調査計画等を踏まえ、必要な人員を把握した上で、ま
ずは庁内の他課の応援を受ける等の対応を取り、なお不足する場合には、他の
地方公共団体や民間団体等に応援を要請します。その際、「応援要請業務の内
容」「応援要請の人数」「応援要請の期間」を明らかにします。
◇ 「応援職員の受入体制の確保」では、応援職員向けの資機材や業務マニュア
ル、活動スペースを確保するとともに、応援職員のための宿泊場所や移動手段
について、応援元の地方公共団体と連携して確保します。
◇ 「応援職員の受入」では、具体的な受入の手続きや応援職員への情報共有の
方法、必要な研修方法などについて定めておきます。
◇ 「応援職員の管理」では、応援職員への指揮命令系統や、応援職員の調査品
質の管理方法、応援職員が交代する際の引継方法などについて整理します。
◇ 「応援の終了と精算」では、応援終了の手続きと精算方法について確認し
ます。
住家被害認定調査等の実施に必要な人員の確保に関し、災害対策基本法に基
づく職員派遣(法第2章第4節)又は応援(法第67条等)の規定を活用するこ
とが可能です。
*参考:災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)(抄)
(職員の派遣のあつせん)
第三十条 略
2 都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要が
あるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対
し、それぞれ、地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣につ
いて、又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第九十一
条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定
する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の
職員に限る。)の派遣についてあつせんを求めることができる。
3 略
(職員の派遣義務)
第三十一条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び
市町村長等並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前二条の規定による
要請又はあつせんがあつたときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障
のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
(他の市町村長等に対する応援の要求)
第六十七条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合におい
て、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市
町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を
実施するための応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援
を拒んではならない。
2 略
(都道府県知事等に対する応援の要求等)
第六十八条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合におい
て、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等
に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。
この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都
道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒ん
ではならない。
②応援の要請
被害認定調査に必要な人員を把握した上で、庁内他部署からの応援では対応
することが困難である場合、他の地方公共団体や民間団体等に応援を依頼し
ます。
また、庁内職員のみでは被害認定調査に関するマネジメントが難しい場合に
は、マネジメント支援に関する人材の応援要請を行います。
なお、応援要請は、必要と判断した時点で「躊躇なく」かつ「速やかに」
実施することが重要です。
*参考:応援の受入開始時期
・ 令和2年に実施した受援団体に対するアンケート調査結果によると、住家
の被害認定調査に関する行政からの受援は、マネジメントに関する内容を除
き、発災から1週間~2週間を経過した頃に受入を開始している団体が多い。
応援要請は、各地方公共団体における「受援計画」に定める方法に沿って行い
ます。通常は、被害認定調査を担当する部署から危機管理部門や人事部門等の
庁内全体の応援要請の窓口となっている部署に対し、必要な人員等の情報を伝
達し、庁内全体の窓口となっている部署が意思決定者の承認のもと、他の地方
公共団体や民間団体に要請を行います。
③応援職員の受入体制の確保
応援職員の派遣要請を行うと同時に、応援職員を受け入れる準備を整えます。
◇ これらは、事前に取り組んでおくことが望ましい内容です。事前準備の詳細
は「第7章3.受援体制の構築と事前の準備」(p.228)を参照して下さい。
応援職員の受入準備として、「応援職員等の執務スペース」「資機材や各種
ニュアル」「移動手段、宿泊場所」の準備・手配が必要です。
④応援職員の受入
応援職員を受け入れる際には、受付を行い、団体名や氏名・活動期間・宿泊
場所・移動手段などについて把握しておくようにします。
応援職員の到着後、最初の打ち合わせにおいて、被災地の状況や応援職員に
依頼する業務の内容等を説明する必要があります。
⑤応援職員の管理
応援職員に対しても指揮命令系統を明確にし、調査班の編制や調査対象エリ
アの割り当て、調査上の留意点の共有(ミーティングの実施)、安全管理等の
管理業務を行います(第3章1.調査全体の管理を参照)。
また、調査の進捗状況や発生した課題などがないかについて日々把握し、進
捗状況等により職員数が不足する場合は、新たな応援要請を行う必要があり
ます。
応援職員の交代がある場合には、業務内容の引き継ぎを行います。
⑥応援の終了と精算
被害認定調査が終了、もしくは自らの団体内の職員のみで対応可能な状態と
なるなど受援の必要がなくなった場合には、応援団体と調整を行い受援終了の
判断を行います。
受援が終了した場合には、庁内全体の窓口となっている部署にその旨を連絡
し、その後当該担当部署において、必要に応じて経費精算の手続きを行うこと
となります。